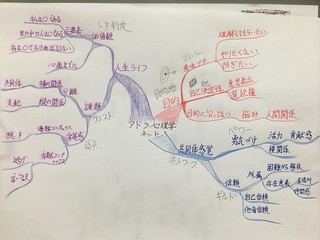犯罪を防ぐのは、犯罪は臆病からの行動と認識させる
共同体感覚が弱いと友人を作らなかったりする、
それゆえ問題行動が目立つ
学校へいく為の準備(共同体感覚)を怠った結果
罰や説教で変えることはできない。
吃音の傾向→人と交わりたい。人と交わりたくない
聴衆の前での緊張、劣等感から。
聴衆と自分を信頼できると問題ない。
岩井 俊憲
日本能率協会マネジメントセンター
売り上げランキング: 12,290
日本能率協会マネジメントセンター
売り上げランキング: 12,290
劣等感の強い子は自分より強い子を排除し弱い子と遊ぼうとする。
優越感から盗みを始める子もいる、欺いていると思い自分が優れていると思う
共同体感覚があってこその優越性の追求
成功しようという野心を持っているという意味で優越性を追求する劣等コンプレックス→自分より可愛いがられる姉がいた、何らかの方法で成功したい
優越性コンプレックス→私だけ優れていれば良い
劣等コンプレックスの補償として優越性コンプレックスが存在する。
ダメな自分を開き直るような感じです。私だけが持っているダメなところ、他の人にはないダメなところみたいな。
あえて結婚できない人を選ぶのは劣等コンプレックスを感じさせる。
優越性コンプレックスは結婚で得られないと別の方法を探す。
それが潔癖など。
(一番大事なのは清潔だ)→世界でただ一人清潔なのは自分だ。
自分だけが清潔と信じており他の人を非難する。(健康な食事もそうなのか)
野田 俊作
創元社
売り上げランキング: 29,808
創元社
売り上げランキング: 29,808
常に緊張感を感じてる、劣等感などから他の人が自分より人気あるとか何かを成し遂げようとしてることに困難を感じ、それを避けるために孤独を選ぶ。
ライフスタイルの矯正は助言などによるが、助言は利害関係のない人からの方が良い
劣等感は取り除けない、
取り除く必要はない↓
目標を変えること
自分を過小評価することで劣等感を減らそうとする、過度の緊張感を持っている。
他人に関心を持てないので「くだらない連中だな、楽しませてくれないな、興味わかないな」的な考えになる
弱さを強調して相手を支配する、不平や苦しみを言って相手を支配→甘やかされ
(一つの行動だけで判断できない、寄りかかるなどは支えられたいのか)
母親と結びつきたい→オネショ、夜泣き
断念したがる子供→家族の中心になっている子が多い、皆が世話をし励ます。
支えられ続けることがこの子の優越性の目標。他人を支配したい欲求
→劣等コンプレックスの結果(自分自身の力を疑っている)
羨望は良いが嫉妬は危険
子どものライフスタイルの形成は就学前
問題行動のある子、人生の問題に対して準備できず野心的で支配者になりたがっているが社会のために力を持ちたいと思わない
→人生の問題に関心を持たない
→臆病、甘やかされて育つ
問題行動の子どもの特徴、注意深くためらう事が多い。人生の課題の前に挑むこともせず、立ち止まり、延期する、気晴らしばかりする。
困難をコントロールできるようにする事が大切
甘やかされた子供は学校生活などで劣等コンプレックスを感じ親に自分を欺かれたと思う。(本当の能力を教えてもらえなかったから、こんなに出来ないとは知らなかった)
劣等感が大きすぎなければ、
目的を達成する為に他人に関心を持つ
岸見 一郎
中央公論新社
売り上げランキング: 15,997
中央公論新社
売り上げランキング: 15,997
共同体感覚と社会適応は劣等感の正しく正常な補償
劣等コンプレックス→もしも〇〇なら、出来るのに!、ずるさ、用心深い、知ったかぶり、大きな課題に背を向ける、多くの原則と規則によって行動を狭い範囲に限る。また奇妙な関心を発達させたりする。怠惰は劣等コンプレックスの表れ
→盗む、無防備や不在に漬け込む、嘘をつく、真実を言う勇気がない。
劣等コンプレックスから優越コンプレックスへの移行、他人の人が自分にかかりっきりになる事で(奉仕される)優越した者になることができる。
劣等コンプレックスは他人を排除しようとする
性格が遺伝し成功が生まれつきの能力ならカウンセラーは必要なくなる
盗みは自分を豊かにするための行動、自分の権利を奪われていると思わなければ、自分自身を豊かにしようとは思わない(愛情不足を感じる、希望がないと感じる)
(愛される権利、希望がある感じれる権利)
盗みを見つからないようにするのは、盗みを成功させたいから、自分を豊かにしたいから。盗みを見つかるようにするのは、盗みの罰にる勇気を表したいのか。
恋愛と結婚
性の本能についての訓練が必要他人に関心を持ち、他人の目線になって考えたり感じることが必要。
共同体感覚が重要
甘やかされた子供は性的に発達しない。
性生活を社会的に有用な目標に結びつけることが大事
劣等感は努力と成功の基礎
適切な優越性の目標を見出せない時に劣等コンプレックスが起こる劣等コンプレックスは逃避を引き起こし、逃避の欲求は優劣コンプレックスの中に表現される。優劣コンプレックスは偽りの成功による満足をもたらす
アルフレッド アドラー
アルテ
売り上げランキング: 33,675
アルテ
売り上げランキング: 33,675