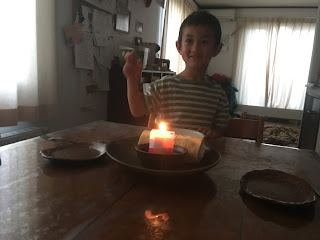ここにご紹介
勉強しなさいを連呼しても効かない
どうしたらやる気を引き出せるのか
勉強でもそれ以外のことでも同じですが、人間が「何かやるぞ」という気持ちになるためにいちばん必要なものは、
「安心感」
自分が「認められている」とか「理解されている」と感じられて、安心感があるときに、「じゃあ、新しいことに挑戦してみよう」とか「ちょっと自分を変えてみよう」などと思えるんです。
だからまず親は、子どものことを理解してあげる。
そこでお子さんは安心感を抱いて「やってみよう」という勇気が湧いてくる。
そういうふうになるのが大事
――具体的には、どんなふうにすればいいんでしょう
「気づいて励ましてあげる」ということが、とっても重要です。例)うちの娘は漢字がすごく好きなんです。お兄ちゃんもいるので、どんどん自分で新しい漢字を覚えていっちゃう。
だから、同じ漢字を何十回も書かないといけない、という漢字の宿題が、すごく嫌だと言うんですね。まぁ、あれはあれで、精神鍛錬にはなると思うんですけれど。
でもうちの娘は気が強いので、3回くらい書いたらあとは、「もうおぼえました」と書いて、白紙で提出するんです。
最初は僕も「これはどうかな?」と思ったのですが、妻と話して「これはこれで、いいんじゃないの?」と思うようになりました。
自発的に勉強をするように!
そこで担任の先生に「こういう状況で、どうしてもやりたくないと言うので、すみません」と説明をしたら、先生も「まぁそれは、花丸はあげられないけど、認めますよ」というふうに対応してくれたんです。そうしたら娘はそのうち、自分で漢字の成り立ちとか、熟語を調べたりして、その空欄を埋めるようになったんです。
これは成功した例かな、と思います。先生とコミュニケーションをとって、僕も励ましたりしたので、娘は「私のことを認めてもらえているんだ」と感じてやる気を出して、自分から次のステップに進むことができたんですよね。
――「どうしてもやる気になってくれない!」というとき
やっぱり「騙しだまし」やっていくしかないんだろうな、と思います。いくら「勉強しなさい」と親が言っても、あまり効果がないことは、皆さんよくご存知でしょう
だからお尻を叩くだけではなく、騙しだましでもいいから、「あ、それうまくできてるじゃない!」というふうに乗せることも大事です。
いろんなツールを使って、子どもの興味を引き出すようなやり方をできるといいですね。
勉強のときの姿勢。
「勉強に対する姿勢」ではなく、本当に姿勢が悪いんです。私としては、テーブルや机に向かってきちんと座って勉強をしてほしいんですけれど、立ったままやったりするんです。あとは、リビングのフローリングの真ん中で「丸まってるな?」と思ったら、そこで勉強していたりして(苦笑)。
勉強を全然しないときには、「何でもいいからやってほしい」と思いますけれど、実際にし始めると、今度は「やり方がちょっと」と思ってしまう。
知らず知らずのうちに、要求のハードルが上がっていくところはありますね(笑)。
でも、立ったままやるのも、僕はいいと思いますよ。
僕も家で仕事をするとき、立ってやったりしてますからね。ずっと座ってパソコンに向かっていると疲れてくるので。
ストレスは人それぞれ感じるものが違う
こんな調査結果もあります。アメリカの男女共学の小学校で、男の子と女の子に分けて、それぞれ好きなように授業を受けさせたんです。そうすると男の子たちは、寝そべったままとか、立ったままで授業を受けたそうなんです。だけど、その男の子たちのクラスは、成績が上がったんですって。
男の子はまず、じっと座っているということ自体が窮屈で、すごくストレスなんですね。だから自由な体勢にさせてストレスを減らし、勉強に集中させる、というのもひとつの手じゃないかと思います。
寝転がってやってもいいし、立ってやってもいい。もしたまたまテーブルに向かって座ってくれたら「おぉ! ちゃんとやれているじゃない!」と励ましてあげる。そこを見逃さないのもポイントですね。
お子さんが言うことを聞かなくなってきたのは、決してこれまで甘やかされてきたからとか、そういうことではないと思います。
子どもは親がどう反応をするか見ている
成長過程において、実験をする時期があります。ちょっと悪い言葉を覚えてきて、「この言葉を使うと、どういう反応があるのかな?」とか、「こういう悪態をついていると、ママはどんな顔するんだろう?」とか、試しているのかもしれません。
そこで親が珍しく怒ったりしたら、
息子さんは「あぁ、ママでも怒ることがあるんだな、これは時々気をつけなきゃいけないぞ」とか、「こういう言葉は言うべきじゃないのか」などと学ぶわけです。
そういうプロセスも必要なので、あんまり「こうしなきゃいけない」という正解を求めなくていいんじゃないでしょうか。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
僕は○○してほしいとか、○○になってほしいとか様々な期待を子供たちに押し付けているのを最近気づきます。
その押し付ける期待が子供たちにとっては邪魔でありウザイということになっているんだなぁと
子供は子供であるべき姿なのですが、親としての価値観を子供に押し付けすぎるのも考え物であると感じました。