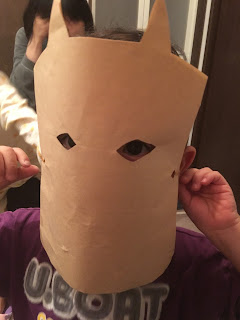様々な親の期待や希望、そういったものが子供への声掛けになったりします。
○○になってほしい
○○やってほしい
○○しないから
○○になるように
どうして伝わらない
どんな言い方がいいのか
何が悪かったのか
そして僕がよくやってしまうのが、結果を想定して声をかけること
片づけてと声をかける
↓
子供が片づける
これは当たり前ですが、この声掛けにより片づけることを条件として伝えている
・片づけてと言ったので片付ける行動をする
前提として声をかけてます。
結果を意識して伝えてる
言い方を変えても結果的に「子供が片づける行動をする」という結果を意識して伝えています。
結果を意識しているので
片づけると思って伝える。
↓
実際に片付いていることはない
↓
何度も伝えたり、最終的に怒ったり
こういった声掛けに異議を唱えるつもりはありません。
ただ声をかけたからと言って、
その効果をすぐ期待してしまう悪い癖が
僕にはある。
怒りに代わる
言ったからには○○してほしい。
○○っていったのにやってない。
何度も○○って言ってるよね!
これらは全て言ったことが伝わり、子供が理解し行動してくれると信じているから。
でもその信じてる気持ちが、行動に出ていないことで
絶望に代わり、
怒りに代わる。
何度も何度も怒られた子供は自己肯定が下がり、実行する意欲がさらに低下
意欲が下がったことで他の行動やもできず、
同じことを何度も言われ、
出来ずが続き再び怒られ・・・
悪循環ですね。
魔法の言葉を探す
子供たちにどういえば伝わるのだろうと考えてしまい、
魔法の言葉を探しますが、
ハリーポッターでもない限り魔法は難しい・・・
何を伝えればいいのか
なんて言えばいいのか⁉
伝わるときもあれば伝わらないときもある。
片づける時もあれば片づけないときもある。
つまり子供次第。
そうなんです。
子供次第なんです。
だから、大人であり親である僕がどう考えて言葉を伝えても、子供次第ってことが前提にあるんです。
もう一度言います。
子供次第。
伝える言葉をアレこれと探すよりも、受け取る子供に意識を向けないと意味がないってこと。
片づけたり、
廊下を走らないと理解したり、
やらないといけないことを理解したり。
こういったことを
なぜ受け止めれないのか、
どうして行動に移せないのか、
なぜ大人の声が届かないのか
ここに視線を合わせていくことが大事だと感じてきました。
そのために何が必要なのか⁉
日常生活として大前提にしないといけない部分なのかな?と最近よく考えます。
原屋 文次
かもがわ出版 (2016-10-14)
売り上げランキング: 29,456
かもがわ出版 (2016-10-14)
売り上げランキング: 29,456













![斎藤公子の保育論[新版]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41L7J4DrQ4L._SL160_.jpg)












![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17953803.4018bcaa.17953804.24bb46d6/?me_id=1198639&item_id=10014606&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzakkashop%2Fcabinet%2Fimagebox29%2F30531-4.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzakkashop%2Fcabinet%2Fimagebox29%2F30531-4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)